
障害児が学校に行くのを嫌がったら、助けてのサインです。見逃さないようにしましょう。
-
<目次>、いじめられる。学校を休む。
- 1、発達障害の特徴の具体例
- 2、うちの子の場合は。(障害を持つ子)
- 3、改善方法の具体例、家庭でやること。
- 4、改善方法の具体例、学校に期待すること。
発達障害の特徴、具体例。
いじめられる。学校を休む。
発達障害、知的障害の子は、いじめの対象となることが多いです。いじめとまでは言えなくても、面白がってからかわれたりします。
障害児の場合は、本人には、いじめの自覚がないけど、いじめられている場合もあります。
- 勉強ができないとからかわれる。
- 走るのが遅いとからかわれる。
- バカと言われる。
- ベランダから飛び降りろと言われる。

発達障害、知的障害を持つ子は、元気に学校に通っているように見えても、障害のため学校でいろんな困ったことが起きています。
その結果、学校に行くのを嫌がる。登校拒否で不登校になる。具合が悪くなさそうなのに、朝になると頭やお腹が痛いと言う。学校に行きたくないと言う。
いじめの他にも、学校が嫌になる原因は、
- お友達がいないこと。
- 先生から注意されること。
- 勉強や運動についていけないこと
いろんなことが考えられます。
うちの子の場合は。
(広汎性発達障害、軽度知的障害児)

うちの子は、小1と小2で、嫌がらせを受けたけど、その後は先生のおかげで楽しく通学できました。
うちの子も、小学校の低学年で、嫌がらせがありました。
学校から帰ってきて「バカって言われる。」と泣いたことがあります。
しかし、担任の先生に相談すると、すぐに嫌がらせは、なくなりました。しっかした担任の先生だと、クラスの雰囲気をコントロールしてくれます。うちの子は、先生に恵まれて、毎日楽しく登校することができました。
うちの子が発達障害、知的障害でも、普通学級だったので、学校側の配慮で、しっかりした担任の先生のクラスに割り当ててくれてたようです。感謝ですね。
いじめられる。学校を休む。改善方法の具体例、小学生の発達障害

いじめを予防する、学校に通わせるための改善例を紹介します。
いじめを発見するために、家庭でやること。
学校の出来事を毎日話す。
親子で学校での出来事について、毎日話すようにしましょう。
楽しかったこと3つ、悲しかったこと3つ、子供に話をさせましょう。子供の話を聞く時は、問い詰めたりせずに、何でも相談できる雰囲気を意識しましょう。
発達障害、知的障害を持つ子は、会話が不得意で上手く説明できないこともあります。家事の片手間で子供の話を聞くのではなく、3分間だけでも集中して子供の話を聞いてあげましょう。会話が苦手な障害児は、会話の練習にもなります。
子供と交換日記をする。
学校での出来事などを子供に書かせて、親子で交換日記をしましょう。
困ったことがあっても、言葉で上手く伝えられない子の場合でも、日記やノートに書くことならできる子もいます。1日を振り返り、楽しかったこと、悲しかったことの、両方を書かせるようにしましょう。
普段は仕事で帰りが遅くて、あまり会話ができない父親がやるのも効果的です。いじめを早期発見できるだけでなく、会話だけでは気づけない子供の気持ちを知ることができます。
同じクラスの子に学校の様子を聞く。
同じクラスの子に学校での様子を聞きましょう。
同じクラスの子供に直接聞けない場合は、そのお母さんに聞いてみましょう。担任の先生の前ではいじめなくても、先生に隠れていじめている場合があります。担任の先生が気づいていないことも、同じクラスの子なら、気が付いている場合もあります。
障害児本人、担任の先生、それだけの話で判断するのではなく、ママ友などから、いろんな情報を聞けるようにしておきましょう。ママ友がいない方は、PTA活動や、地域の自治会の活動に参加して、同じ学校の子、そのお母さんと知り合いになっておきましょう。
不登校になった子を、学校に通わせるために、家庭でやること。
優しくしてあげる。
学校に行きたくないってことは、学校で嫌な思いをしているってことです。
障害を持つ子にとって学校に通うってことは、普通の子と違って、とても大変なことです。できないことを頑張って、無理をして努力してきたんです。ここまで頑張ってきた子供に、家庭では優しくしてあげましょう。
家庭を心が休まる場所にすることが大切です。発達障害、知的障害を持つ子が、また学校で頑張ろうって気持ちになれるように、家庭を癒しの場所にしてください。
しばらく休ませる。
「明日1日、休もうね」期限を決めて、しばらく学校を休ませてみましょう。
原因がわからないのに、無理に学校に行かせるより、期限を決めて、一旦学校を休ませるのも効果的です。だらだら休み続けないように、しっかりと期限を決めてから、学校を休ませてリフレッシュさせてあげましょう。
学校を休ませている間に、学校を嫌がる原因を見つけて対応を考えましょう。
原因を見つける。
学校を嫌がるようになった原因を見つけましょう。障害児本人の話をじっくり聞きましょう。
焦ってあれこれ質問ばかりにならないように、話をよく聞くようにしましょう。
障害児本人に聞いても原因がはっきりしない場合は、学校の先生や、同じクラスのお友達、お友達のお母さんなど、いろんな人に聞いて原因を見つけましょう。
原因を解決する。
いじめが原因なら、先生と一緒に対応を考える。友達がいなくて面白くないのが原因なら、休み時間の過ごし方を担任の先生に相談しましょう。
担任の先生に叱られるのが原因なら、担任の先生に注意の方法を配慮してもらい、校長先生や教頭先生にも相談しましょう。
勉強についていけないのが原因だったら、普通学級から支援学級への変更も検討してみましょう。支援学級への変更は、教科単位での変更など、いろんな方法があります。発達障害、知的障害を持つ子にとって何がいいのか、学校の先生とよく相談しましょう。
いじめを予防するために、学校に期待すること。
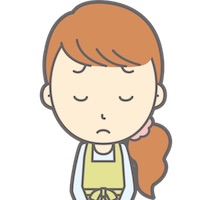
障害のことを先生にお願いしましょう。
発達障害児への配慮
学校に期待することは、必ずやってもらえるわけではありません。担任の先生にとって、負担になることも多いため、先生とよく話し合って希望を伝えましょう。
いじめを見たらやめさせる。
学校でいじめを見つけたら、すぐに先生にやめさせてもらいましょう。
障害児本人がいじめられている自覚がなくても、いじめ、からかいは、すぐに止めましょう。
発達障害、知的障害を持つ子の中には、「いやだ」と言えない子もいます。嫌がらないから、からかった、「やめて」と言わないから、やめなかったという、いじめっ子の言い分を認めず、いじめは絶対にダメなんだと指導しましょう。
いじめをなくす雰囲気つくり。
クラスでいじめをなくす雰囲気をつくることが大切です。小学校では担任の先生の影響はとても大きいものです。
先生が障害児の長所を褒めると、クラス全体が先生の真似をします。発達障害、知的障害を持つ子が活躍できるように、先生がしてやりましょう。
勉強や運動だけじゃなく、係活動や、給食当番、日直の仕事、掃除の時間、ちょっとしたことで構わないので、お互いの長所や頑張りを褒めあうクラスの雰囲気をお願いしましょう。
不登校になった子を、学校に通わせるために、学校に期待すること。
発達障害児への配慮
学校に行くのを嫌がり、学校を休むようになったら、家庭だけの対応で改善することは、まずできません。担任の先生や校長先生なと学校とよく相談して、改善方法を考えましょう。
学校の先生と話すときは、感情的になっても問題は解決できません。親として必死になるのは当然ですが、落ち着いて先生方と協力して解決策を見つけましょう。
先生やお友達に原因を考えてもらう。
学校の先生や、同じクラスのお友達に、学校を嫌がるようになった原因を考えてもらいましょう。
学校が嫌で休んでいることを隠すのではなく、クラスのお友達に学校が嫌になっていることを知ってもらいましょう。
学校を休むまで気にしてなかった友達が、これからは気にかけてくれるかもしれません。何気ない気持ちでからかっていたお友達が、反省してやめてくれるかもしれません。何事もなく済ますと、今までと何も変わりません。学校を休んだことが、いいきっかけになるようにしましょう。
休み明け、楽しく受け入れてもらう。
休み明け、また学校に行った時には、楽しい雰囲気で受け入れてもらいましょう。
学校に再び行ったときに、また誰も話相手がいないと、今まで以上に孤独を感じてしまいます。担任の先生に、クラスみんなが待っていたという雰囲気をお願いしましょう。
ダメな例、発達障害児には効果なし。
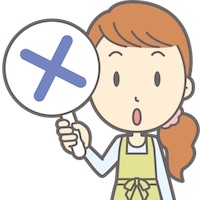
障害児に効果なし。
いじめられたことを叱る。
いじめられる方にも責任がある、こんな叱り方は絶対やめましょう。いじめるのが悪いのです。いじめた子を叱りましょう。
発達障害、知的障害を持つ子は、いじめられたくて、いじめられてるわけではありません。障害のため本人にはどうしようもないのです。もし自分のものが盗まれた時、泥棒より、自分が悪いと納得できますか?いじめられるのが悪い、こんな考えはやめて、いじめられる子のことを考えてあげましょう。
やり返させる。
「いじめられたら、やり返せ」障害児がいじめられた時に、やり返すように子供に言うのはやめましょう。
発達障害、知的障害を持つ子は、いじめられても、何もできずに困っているのです。障害のため、やり返したり、言い返したり、無視したりできないのです。
困っている子に、無理なことを言って、さらに困らせるのはやめましょう。障害児本人にやり返せと、無理を言うのではなく、いじめがなくなるように考えましょう。
無理に学校に通わせる。
学校に行くのを嫌がる障害児を、無理に学校に通わせるのはやめましょう。発達障害、知的障害を持つ子は、できないことを努力して、頑張っています。学校に行けないのは、サボっているのではなく、障害のためなのです。力ずくで学校に連れて行ったりするのは、やめましょう。
長期間休ませる。
一旦学校を休ませて、リフレッシュさせるのは効果的ですが、ダラダラ長期間学校を休ませるのはいけません。
休みが長くなると、学校に戻りにくくなりますし、長期間休ませても、問題は何も解決しません。どうしても学校に馴染めないと判断したら、長期間休ませるのではなく、普通学級から支援学級への変更、支援学校への変更を考えましょう。
長期間ずっと学校を休むより、環境を変えて新しい学校生活をスタートさせましょう。発達障害、知的障害を持つ子への特別支援教育制度を活用して、子供の将来のために何が役立つかを考えましょう。














